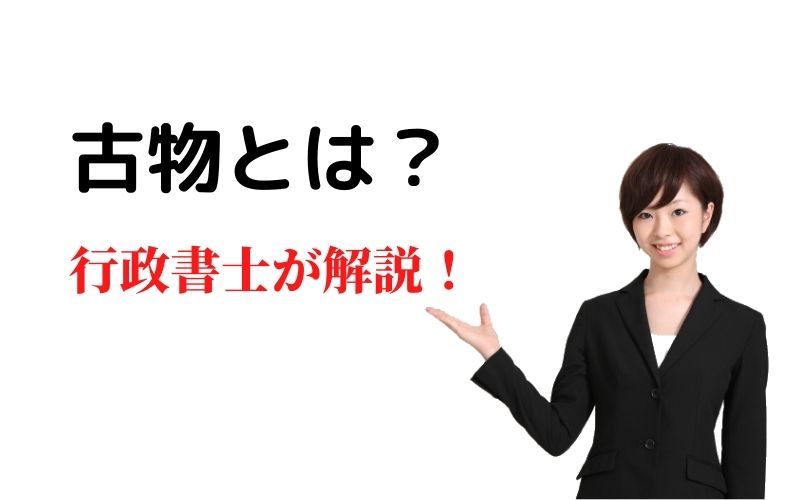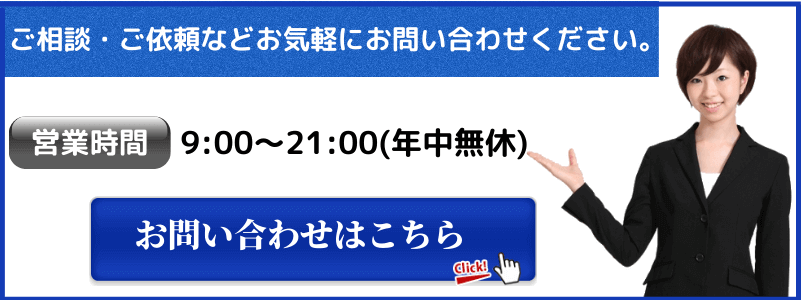中古品の売買をお考えの方。
『古物って何?』と疑問に思っていませんか。
これから古物商になるなら『古物』について知っておきましょう。
- この記事を書いた人
現役の行政書士。
古物商許可の相談実績は1000件以上あります。
そこでこの記事では古物についてわかりやすく解説します。
記事を読むことで古物について理解できます。
古物とは?わかりやすく解説

まず古物とは何かを見ていきましょう。
古物営業法第2条で古物を次のように規定しています。
「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたもの
引用:e-Gov法令検索
簡単にいうと、古物は次の3つに分類されます。
- 一度使用された物品
- 使用されない物品で使用のために取引されたもの
- これらいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの

①一度使用された物品
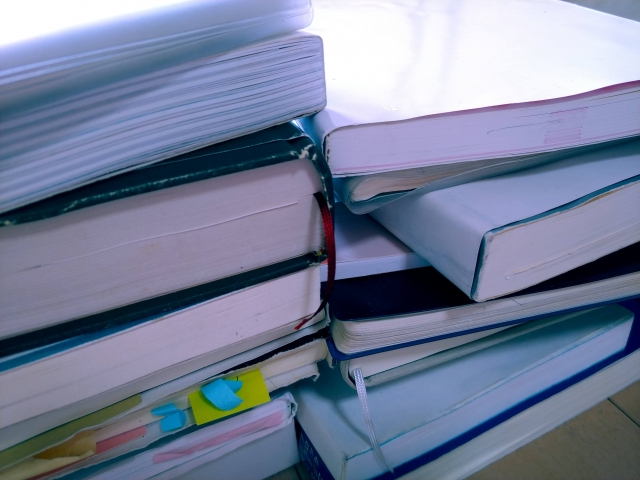
一度でも使われた物は古物となります。
例えば次のようなものです。

②使用されない物品で使用のために取引されたもの

使うために購入したが、一度も使うことがなかった。新品状態で未開封のもの。新古品といいます。
例えば、次のようなものです。
③これらいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの

古物の用途を変えず、修理や手入れを行ったものです。
具体例を見ましょう。
- 古物とは【まとめ】
- 一度でも使ったもの
- 使用するために購入したが、一度も使わなかったもの
- 古物の用途を保ったまま、修理や手入れをして再び使える状態にしたもの
新品は古物に該当するの?

新品は古物に該当しません。しかし、新品の定義が曖昧なので解説します。
メーカーや工場などから直接新品を仕入れたものは古物に該当しません。工場で作られた商品をそのまま仕入れる場合です。
しかし、一度でも人の手に渡ったものは新品であっても古物に該当します。
別の言い方をすると、一度でも市場で取引されたものは古物です。
13種類の古物の区分
古物営業法では古物を13種類に分類しています。
| 美術品類 | 絵画、彫刻、工芸品、骨董品、水彩、芸術写真、アンティーク等。
美術的価値があるもの。 |
|---|---|
| 衣類 | 古着、着物、和服類、子供服、布団、帽子等。
身にまとうもの。 |
| 時計・宝飾品類 | 時計、腕時計、置時計、眼鏡、宝飾品、宝石類、アクセサリー等。
身につけて使う物。 |
| 自動車 | 自動車、タイヤ、エンジン、マフラー等。
車体だけでなく、部品も含む。 |
| 自動二輪車及び原動機付き自転車 | バイク、原付バイク、タイヤ、エンジン、マフラー等。
バイク本体だけでなく、付属部品も含む。 |
| 自転車類 | 自転車、タイヤ、かご、サドル等。
自転車本体と付属の部品も含む。 |
| 写真機類 | カメラ、レンズ、望遠鏡、ビデオカメラ、双眼鏡等。 |
| 事務機器類 | パソコン、タイプライター、コピー、電話機、ファックス、シュレッダー、ワープロ等。
事務作業で使用する機器のイメージ。 |
| 機械工具類 | 電気類、工作機械、土木機械、化学機械、家庭電化製品、ゲーム機等。
電気によって動く機械や器具等。 |
| 道具類 | 家具、CD,DVD,ゲームソフト、運動用具類、楽器等の家庭用品。
他の12種類に該当しないもの。 |
| 皮革・ゴム製品類 | カバン、靴、バック、財布等。
皮革(ひかく)とは動物の皮を加工したもの。 |
| 書籍 | 古本、雑誌等。 |
| 金券類 | 商品券、乗車券、航空券、ビール券、郵便切手等。 |
古物に該当しないもの
次のものは古物に該当しません。
- 総トン数20トン以上の船舶
- 航空機
- 鉄道車両
- 重量が1トンを超える機械で土地や建造物等に固定され、容易に取り外しができないもの
- 重量が5トンを超える機械で自走やけん引ができないもの
上記の『大型機械類』は古物に該当しません。
食品やお酒など消費して無くなるものも古物に該当しません。
古物を売買する時の注意点
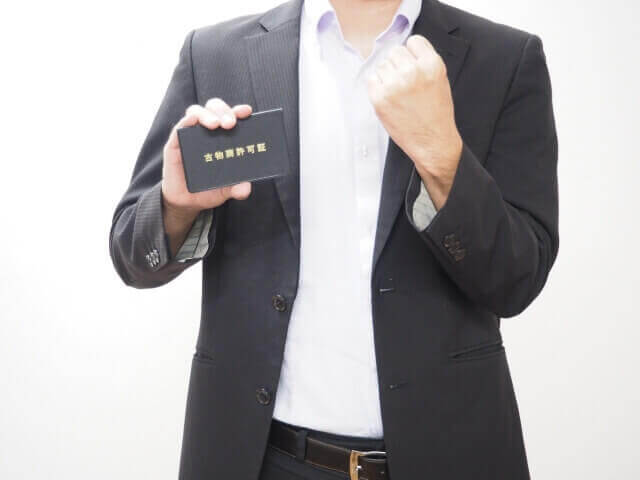
古物の買取・販売を行う場合は『古物商許可』が必要です。
ビジネス目的で古物売買をするなら事前に『古物商許可』を取得しなければなりません。
次の項目に該当する行為を行う場合は『古物商許の取得が必要』です。
- 古物を買い取って売る
- 古物を買い取って修理して売る
- 古物をレンタルする
- 国内で仕入れた古物を海外へ輸出

≫参考:古物商許可証とは【行政書士が解説】取得方法やメリットも説明
無許可営業を行うと3年以下の懲役または100万円以下の罰金に科される可能性があります。
古物商許可はメルカリ利用時に必要?

多くの方がメルカリを利用しています。
メルカリを使う場合、古物商許可は必要なの?と疑問に思う方がいます。
結論、利益目的でメルカリを使用する場合、許可は必要。
不要品の処分目的でメルカリを利用する場合、許可は不要です。

≫参考:古物商許可はメルカリする時に必要?【行政書士が解説】
古物商許可がいらない場合
古物商許可がいらない場合は次のとおりです。

古物商許可申請でお困りなら行政書士に相談
行政書士は申請者に代わって古物商許可の申請手続きができます。
申請書類の作成や書類収集を行政書士に任せることで面倒な手続きから解放されます。
【東海地方の方へ】お悩み解決に繋がる無料相談窓口はこちら
行政書士塚田貴士事務所では、これから古物商許可を取得する方を対象に無料相談をおこなっています。
- 中古品の売買をしたい!
- 許可が欲しいが手続きをする時間がない!
- 古物商許可を代わりに取得してほしい!
上記でお困りならお気軽に無料相談をご利用ください。
対応地域は愛知県、岐阜県、三重県です。
古物商許可に関する下記の記事も参考にしてください。