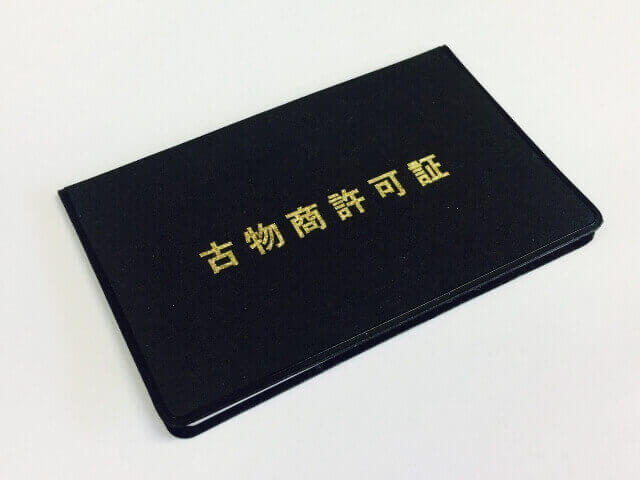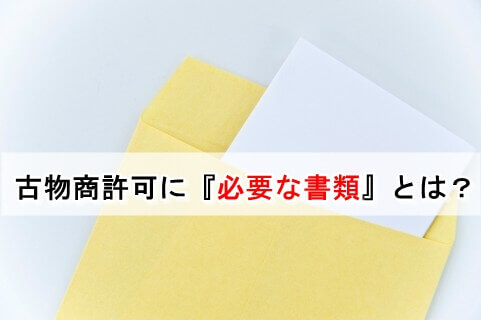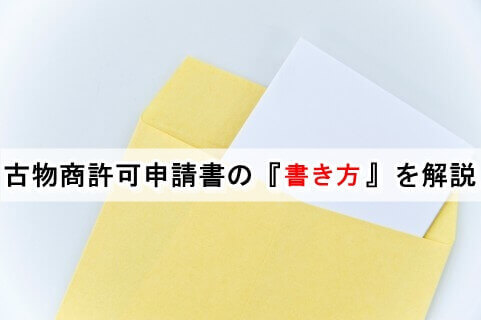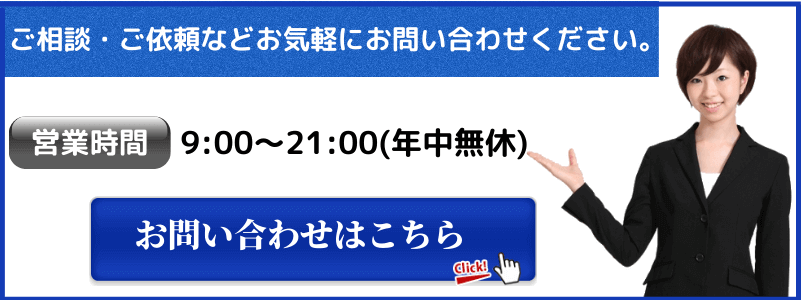- 古物商許可証について知りたい
- 古物商許可証の取得方法は?
- 取得するメリットはある?
古物商に興味がある方。
『古物商許可証って何?』と疑問に思っていませんか。
これから中古品の売買をする予定なら知っておきましょう。
- この記事を書いた人
古物商許可専門の行政書士。
古物商許可の相談実績は1000件以上。申請実績は100件以上。
そこでこの記事では、古物商許可証に関する一般知識を解説します。
記事を読むことで古物商についての知識が深まります。
古物商許可証とは?

古物商許可証とは古物営業が許された公的な証明書です。
利益を得る目的で中古品を仕入れて販売する場合、事前に都道府県公安委員会の許可が必要になります。
都道府県公安委員会の許可を得た証に交付されるのが『古物商許可証』です。

≫参考:古物商とは?【行政書士が解説】許可が必要なケース、申請方法も説明!
そもそも古物とは?

古物とは『一度でも使用された物品』です。つまり、中古品を指します。
古物営業法のなかで古物は13種類に分類されています。
| 美術品類 | 絵画、彫刻、工芸品、骨董品、水彩、芸術写真、アンティーク等。
美術的価値があるもの。 |
|---|---|
| 衣類 | 古着、着物、和服類、子供服、布団、帽子等。
身にまとうもの。 |
| 時計・宝飾品類 | 時計、腕時計、置時計、眼鏡、宝飾品、宝石類、アクセサリー等。
身につけて使う物。 |
| 自動車 | 自動車、タイヤ、エンジン、マフラー等。
車体だけでなく、部品も含む。 |
| 自動二輪車及び原動機付き自転車 | バイク、原付バイク、タイヤ、エンジン、マフラー等。
バイク本体だけでなく、付属部品も含む。 |
| 自転車類 | 自転車、タイヤ、かご、サドル等。
自転車本体と付属の部品も含む。 |
| 写真機類 | カメラ、レンズ、望遠鏡、ビデオカメラ、双眼鏡等。 |
| 事務機器類 | パソコン、タイプライター、コピー、電話機、ファックス、シュレッダー、ワープロ等。
事務作業で使用する機器のイメージ。 |
| 機械工具類 | 電気類、工作機械、土木機械、化学機械、家庭電化製品、ゲーム機等。
電気によって動く機械や器具等。 |
| 道具類 | 家具、CD,DVD,ゲームソフト、運動用具類、楽器等の家庭用品。
他の12種類に該当しないもの。 |
| 皮革・ゴム製品類 | カバン、靴、バック、財布等。
皮革(ひかく)とは動物の皮を加工したもの。 |
| 書籍 | 古本、雑誌等。 |
| 金券類 | 商品券、乗車券、航空券、ビール券、郵便切手等。 |
上記の古物を使って利益目的で売買を繰り返す場合に『古物商許可』が必要になります。
古物商許可証の取得が必要な場合
次に該当する行為を行う場合は古物商許可証の取得が必要になります。
- 古物を買い取って売る
- 古物を買い取って修理して売る
- 古物をレンタルする
- 国内で仕入れた古物を海外へ輸出
転売して利益を得る目的で古物の取引を行う場合は許可が必要です。
古物商許可証の取得が不要な場合

次の項目に該当する行為を行う場合は『古物商許可証の取得が不要』です。
- 自分が使うために買った物を処分目的で売る
- 新品を売る
- 無料でもらったものを売る
- 海外で買ってきた物を日本で売る

古物商許可には『個人』と『法人』の2種類がある
- 個人申請…個人事業主やフリーランスなど個人として古物商許可を取る。
- 法人申請…株式会社や合同会社など法人として古物商許可を取る。
古物商許可を取得する際は、『個人』でやるのか、『法人』でやるのか決めます。
≫参考:古物商許可を個人で取得【完全ガイド】専門行政書士が詳しく解説
≫参考:古物商許可を法人で取る!取得方法や費用、注意点を行政書士が解説
古物商許可証の取り方【4ステップ】

- 申請窓口を調べる
- 申請書類を揃える
- 申請書類を窓口に提出する
- 古物商許可証が交付される
申請窓口を調べる
古物商許可証を取得するには、申請窓口に古物商許可申請の手続きが必要です。
申請先は『主たる営業所の所在地を管轄している警察署』になります。主たる営業所とはメインとなる営業所です。
営業所が1か所の場合、自動的にそこが主たる営業所になります。
営業所が複数ある場合、営業の中心となる営業所が『主たる営業所』です。
申請に必要な書類を揃える
古物商許可申請に必要な書類を揃えていきます。
| 個人申請 | 法人申請 | |
| 古物商許可申請書 | ○ | ○ |
| 住民票の写し | ○ | ○ |
| 誓約書 | ○ | ○ |
| 身分証明書 | ○ | ○ |
| 最近5年の略歴書 | ○ | ○ |
| 定款及び登記事項証明書 | × | ○ |
| URLの使用権限を疎明する資料 | △ | △ |
| 賃貸借契約書のコピー | △ | △ |
- 〇…必須書類
- △…申請状況によって必要
- ×…提出不要
古物商許可の申請手続きを自分で行う方もいます。しかし、申請には書類作成や添付書類の収集など面倒な作業が必要です。
不安な方や、確実に許可がほしい方は古物商許可専門の行政書士に申請代行してもらうこともできます。

≫参考:古物商許可の取得代行を行政書士に頼むと費用はどのくらい?
書類を窓口に提出する

申請書類が揃ったら窓口の警察署へ提出します。
申請の流れは以下のとおりです。
- 警察署の『生活安全課』に行く
- 古物の担当者に書類を確認してもらう
- 19,000円の収入証紙で申請手数料を納付
- 申請手続き終了
収入証紙は警察署内で購入できます。
古物商許可証が交付される
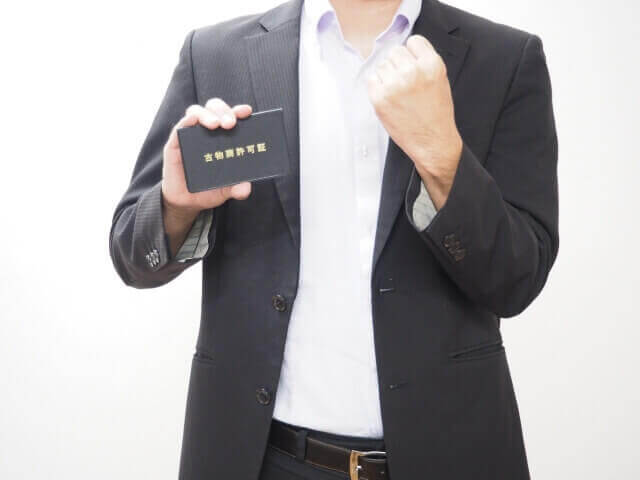
申請後、40日程度の審査期間に入ります。審査期間の経過後、『古物商許可証』が交付されます。
古物商許可証を取得する4つのメリット

- 安心して古物の販売ができる
- 顧客に安心感を与えることができる
- 節税できる
- 許可証に有効期限がない
安心して古物の販売ができる
古物商許可が必要なのに無許可営業を行うと『3年以下の懲役又は100万円以下の罰金』が科されるリスクがあります。
世の中には、知ってか知らずか許可を得ずに古物営業を行う人がいます。
リスクを負いながら事業を行うのは危険です。
顧客に安心感を与えることができる
許可証があることで顧客に安心感を与えることができます。
許可を持っている人、許可を持っていない人。どちらから商品を買いたいですか?
もちろん前者です。
節税できる
個人で古物商許可を取得すると『個人事業主』になります。
個人事業主になると、事業のために購入したものは経費にできたり、青色申告の控除が使えたり節税ができます。
しかし、日本人の多くは会社員です。
会社員は最初に税金が給料から天引きされるので自分でコントロールできません。
一方で、個人事業主は経費や各種控除を活用して最終的に払う税金が決まるので、ある程度自分でコントロールできます。
許可証に有効期限はない
現時点で古物商許可証に有効期限はありません。一度取ってしまえば生涯有効です。
ただし、申請書の内容に変更があった場合は変更手続きが必要になります。
≫参考:古物商許可証を取得する7つのメリット・2つのデメリット【行政書士解説】
【よくある質問】古物商許可証とは?
- 古物商許可証は誰でも取れますか?
- 古物商の資格を取得すると何ができますか?
- なぜ古物商は許可証が必要なのでしょうか?
古物商許可証は誰でも取れますか?
古物商許可証は誰でも取得できるわけではありません。
許可を得るのは要件を満たす必要があります。
古物商の資格を取得すると何ができますか?
事業として、中古品を仕入れて、販売する行為を合法的に行うことができます。
なぜ古物商は許可証が必要なのでしょうか?
古物商許可証がないと、中古品を仕入れて、販売する事業を行うことができません。
無許可営業は罰則の対象になります。
許可証があることで安心して中古品の転売ビジネスを行うことができます。
【まとめ】古物商許可証とは?
古物商許可証について解説してきました。
古物商許可証とは古物取引が許された公的な証明書です。
利益を得る目的で中古品の売買を行う場合は古物商許可証の取得が必要になります。
許可証なしに古物取引を行うと『3年以下の懲役または100万円以下の罰金』になる可能性があります。
許可証を取得するには、申請先の警察署に古物商許可申請が必要です。
古物商許可証を取得するメリットは以下の4点です。
- 安心して古物の販売ができる
- 顧客に安心感を与えることができる
- 節税できる
- 許可証に有効期限がない
古物商許可申請でお困りなら行政書士に相談
行政書士は申請者に代わって古物商許可の申請手続きができます。
申請書類の作成や書類収集を行政書士に任せることで面倒な手続きから解放されます。
【東海地方の方へ】お悩み解決に繋がる無料相談窓口はこちら
行政書士塚田貴士事務所では、これから古物商許可を取得する方を対象に無料相談をおこなっています。
- 中古品の売買をしたい!
- 許可が欲しいが手続きをする時間がない!
- 古物商許可を代わりに取得してほしい!
上記でお困りならお気軽に無料相談をご利用ください。
対応地域は愛知県、岐阜県、三重県です。
古物商許可に関する下記の記事も参考にしてください。