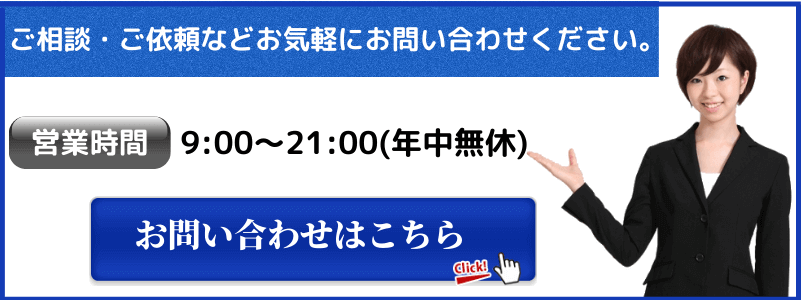- 古物商の管理者って何?
- 管理者は誰でもなれるの?
- どんな人が管理者になるの?
これから古物商許可を取得する方!
『古物商の管理者って何?』と疑問に思っていませんか。
実は古物商の管理者は重要な人です。
- この記事を書いた人
古物商許可の取得専門の行政書士。
古物商許可の相談実績は1000件以上。申請実績は100件以上。
そこでこの記事では古物商の管理者について解説します。
- 結論
- 管理者は営業所の責任者
- 管理者になるのに特別な資格は不要
- 古物商自身が管理者を兼ねることができる
古物商の管理者とは

古物商の管理者とは営業所の責任者を指します。
古物商許可を取得するには原則、営業所の設置が必要。営業所の業務を統括管理するのが管理者です。
管理者の業務内容は次のとおりです。
- 商品や取引の管理
- 従業員の指導・監督
- 警察への捜査協力
従業員を指導・監督できる立場にあり、取り扱う商品を管理するのが管理者の役割です。
古物商の管理者は誰がなるの?

管理者は営業所を統括管理する人なので『古物に詳しい人』がなるべきです。
しかし、実際は古物商許可を取る古物商自身が管理者になるケースがほとんど。
個人事業など、1人で古物商許可を取得して事業を行う場合、申請者本人が管理者を兼ねることができます。
一方、法人で古物商許可を取得する場合、役員が管理者を兼ねることもできるし、別の人を管理者に選任しても構いません。
管理者は1営業所に1名
管理者は営業所ごと1名選任する必要があります。複数の営業所がある場合は、営業所ごと管理者を選任しなければなりません。
原則、同じ管理者は複数営業所を兼任できません。
- 管理者が複数の営業所を掛け持ちできない理由
管理者は営業所に常勤していることが求められます。複数の営業所を掛け持つと常勤性が損なわれます。

古物商の管理者になれない人

法律によって管理者になれない人についての規定があります。
次の1つでも該当する項目があると管理者にはなれません。
- 未成年者
- 破産者で復権を得ていない
- 禁固以上の刑又は一定の犯罪による罰金刑に処せられ、執行後5年を経過してない
- 住居がない
- 過去に不正を働き、古物商許可を取り消されてから5年を経過してない
- 古物商許可の取り消し処分前に許可証を返納した者で返納から5年経過していない
- 暴力団員その他の犯罪組織に属している
- 心身の故障によって古物商としての業務を適正に行えない
現時点で該当する項目があっても期間の経過によってクリアできる場合もあります。
基本的に上記の項目をクリアできれば管理者になれます。

営業所から遠方に住んでいると管理者になれない
管理者は営業所に常勤することが求められています。よって、通勤圏内に住んでいない人は管理者になれない可能性があります。
古物商の管理者に必要な知識や経験
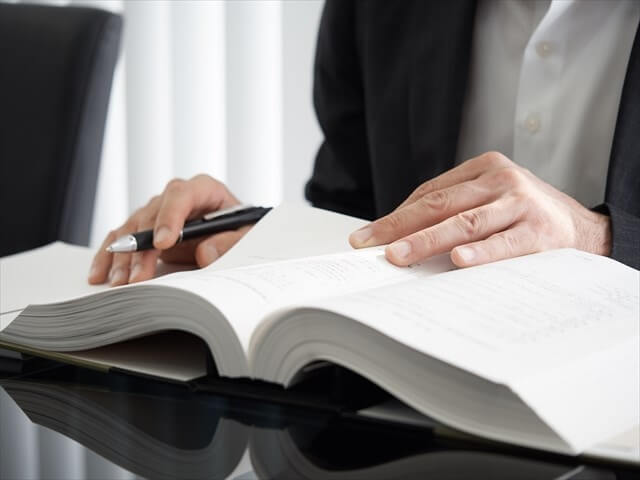
管理者は営業所の責任者。取り扱う古物に関する知識や経験が必要です。
特に自動車やバイクなどを扱う場合は管理者の職歴をチェックされ、知識や経験があるか確認されることがあります。
目安として3年以上、自動車やバイクを取り扱う業務に従事していれば知識や経験があると判断されます。
自動車やバイクは盗難車を持ち込まれる可能性があり、取引額も高額になるため、管理者の『目利き』が重要になります。
つまり、盗難車だと判断できる能力が必要です。
ただし、現時点で知識や経験はなくても、
- 定期的に講習会に参加
- 知り合いに知識・経験のある人がいて相談できる
なら管理者として認められる場合もあります。
時計・宝飾品類
時計や宝飾品も換金目的で盗難品が持ち込まれるケースがあるため、管理者に『目利き』があるか確認される場合があります。
申請では管理者分の書類も用意する
古物商許可の申請をするとき、申請者と管理者が別の人なら管理者分の証明書類も用意しなければなりません。
管理者の証明書類は次の4つです。
- 住民票
- 身分証明書
- 略歴書
- 誓約書
申請者が管理者を兼任する場合は誓約書を除いて1部ずつの提出でOKです。
管理者はいつでも変更できる
管理者はいつでも変更できます。同じ人がずっとやり続ける必要はありません。
- 自分1人でやってきたけど、別の人を管理者にしたい
- 今の管理者が退職するので、新しい管理者を選任したい
管理者を変更する場合は警察署に『変更届出』が必要です。
【まとめ】古物商の管理者について
管理者は営業所の責任者。管理者の業務は次の3つです。
- 商品や取引の管理
- 従業員の指導・監督
- 警察への捜査協力
営業所ごと管理者1人を選任しなければなりません。
取り扱う古物に関して知識や経験のある人が管理者になることが望ましいです。しかし、実際に管理者になる人は古物商自身がほとんど。
たとえ管理者に知識や経験がなくても、講習会を受講したり、詳しい人に相談したりできるなら管理者として認められる場合もあります。
管理者は『変更届出』によっていつでも変更可能です。
古物商許可申請でお困りなら行政書士に相談
行政書士は申請者に代わって古物商許可の申請手続きができます。
申請書類の作成や書類収集を行政書士に任せることで面倒な手続きから解放されます。
【東海地方の方へ】お悩み解決に繋がる無料相談窓口はこちら
行政書士塚田貴士事務所では、これから古物商許可を取得する方を対象に無料相談をおこなっています。
- 中古品の売買をしたい!
- 許可が欲しいが手続きをする時間がない!
- 古物商許可を代わりに取得してほしい!
上記でお困りならお気軽に無料相談をご利用ください。
対応地域は愛知県、岐阜県、三重県です。
古物商許可に関する下記の記事も参考にしてください。